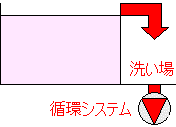| わがまま温泉日記 | お風呂の科学 | |||||||||||||||||||||
▲当世レジオネラ考 ■お風呂の様式 ■お風呂の様式アラカルト ▼塩素投入条例 ▼泉源から湯船まで ▼温泉法 vs 公衆浴場法 |
〜源泉かけ流しと循環のハザマにて〜 | |||||||||||||||||||||
| 半循環 |
レジオネラから始まって、思わぬところで寄り道をしてしまったが、循環風呂にもずいぶん詳しくなった。 |
|||||||||||||||||||||
| ▼三大構成要素 ・源泉投入方法 ・排湯方法 ・循環方法 ▼オーバフロー環水 ▼早見表 |
お風呂の様式 | |||||||||||||||||||||
| 源泉掛け流し ●Thanks to Mr.Yamasemi 「掛け流し」の起源は酒造にあるようです。酒米を研いで水浸するときに、清水を流し放しにしてさらすことらしいです。しっかりさらさないと、糠が残って酒に臭みが出るとか。 |
しばらくは、うまく分類できずにいたが、その原因は「源泉掛け流し」なる情緒的な用語にあった。反面、ここにこそ、からまった糸を解きほぐすカギは隠されていた。かくなる用語を、はじめて用いたお方に頭が下がる。 |
|||||||||||||||||||||
| 三大構成要素 |
すべてに形式的な分類を貫き通すと、次のようになるのだろう。 |
|||||||||||||||||||||
| 源泉投入方法 |
|
|||||||||||||||||||||
| 排湯方法 |
|
|||||||||||||||||||||
| 循環方法 | 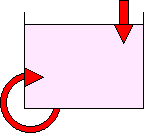
カエルの「親」はカエルである。ワタシの父も温泉好き。その父親が「まわし」なる言葉を用いて温泉の判定基準にしていたのを幼い頃より耳にしていた。そのせいもあり、すぐ「まわし」なる語を使ってしまう。正式には「循環」という。 |
|||||||||||||||||||||
| オーバフロー還水 ●松田忠徳著「温泉教授の温泉ゼミナール」光文社新書p64をご覧あれ。ウッソ〜!と思わず叫んでしまった。 |
厚労省の「オーバフロー還水方式」で想定しているのは、湯船のふちに切られた溝から集水するもの。しかし、実は、オーバフロー還水方式にも二通りあるようだ。 |
|||||||||||||||||||||
| 早見表 |
2つずつピックアップてきた各方式に、「なし」と「併用」を加えて全4方式。後々の説明の都合上、その方式をまとめてみると次の通り。
いよいよ、お風呂の様式を表す番だ。いわばお風呂の型番だ。例えば、わが家のお風呂を表すならば、i0-o0-c2 (ioc#002)となる。あ〜よかった! きちんと表示できている。 |
|||||||||||||||||||||
#000 #002 #012 #013 #110 #111 #112 #120 #130 #210 #211 #310 |
お風呂の様式アラカルト |
|||||||||||||||||||||
| 五右衛門風呂 | 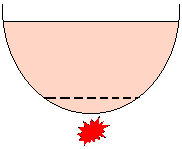 ioc#000 ioc#000源泉投入なし 排湯なし 循環なし 小さい頃は五右衛門風呂の釜焚きを、ずいぶん手伝ったことがある。紙に火をつけ、木っ端に移し、息をフウフウやりながら、木屑に移す。それが燃え始めたら薪をくべる。今でも、こんなにリアルに覚えているくらいだから、さぞや面白かったに違いない。 石川五右衛門、子供と一緒に浸かるに、何ら衛生上の問題はない。ただ、温度管理に気をつけて! |
|||||||||||||||||||||
| 銭湯 | 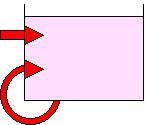 ioc#002 ioc#002加熱した水道水 底面環水 循環湯側壁吐出 ここしばらくは街の銭湯に行ったこともない。エアロゾルが発生する危険も少ないので、同じく循環ならば、こちらの方が好ましい。しかも、銭湯ならば毎日換水、データによるとレジオネラの発生もなし。 ただ、その泉質表示は次亜塩素酸塩泉かも知れないよ^^。 |
|||||||||||||||||||||
| スーパー銭湯 | 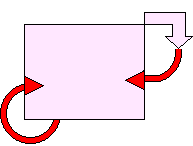 ioc#012 ioc#012加熱した水道水 オーバーフロー環水 循環湯側壁吐出 厚労省「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」では、次のように紹介している。いわば、政府公認の方式。 「浴槽内に浴槽の側壁や底面から湯を吐出させて、浴槽の縁からオーバフローさせた湯を集めてろ過器に戻す方法で、湯が豊富に溢れ出ているように見せる視覚的な効果と、浴槽表面の浮遊物の除去が可能です。節水の目的でも用いられる循環方式です。 この方式は、最近、旅館の大風呂や大型の浴場(いわゆるスーパー銭湯等)で使われるようになっていますが、オーバフローした浴槽水に洗い場の排水を混入させない集水方法としなければなりません。」 浴槽のふちに溝の切ってあるタイプだと思うが、洗い場の排水が混入せぬよう祈るばかり。 |
|||||||||||||||||||||
| 温泉センター | 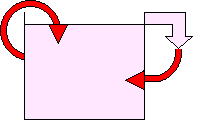 ioc#013 ioc#013入れ替えたときのみ源泉 オーバーフロー環水 循環湯上部投入 滝のように流れ落ちるお湯、湯船のふちからひたひたと溢れ出すお湯。この至福のひとときを追求したのが、この様式。 目からも耳からも楽しめるのはよいのだが、エアロゾルをまき散らすようなもので、レジオネラ対策の点からいっても、大いに問題がありそうだ。 |
|||||||||||||||||||||
| 須川温泉 須川高原温泉 |
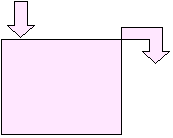 ioc#110 ioc#110源泉上部投入 オーバーフロー 循環なし 源泉掛け流しの典型的なイメージといえば、このタイプでしょ。しかも、豊富な湯量で泉源近くとなると、須川温泉がまず浮かぶ。千人風呂の豪快さといったら、ワタシを捕らえて離さない。 その他、たくさんの「源泉掛け流し」のお湯を、「東北の秘湯」でレポートしているので、よろしかったら、どうぞご覧くださいな。 |
|||||||||||||||||||||
| 松之山温泉 凌雲閣 |
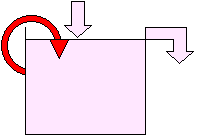 ioc#111 ioc#111源泉上部投入 オーバーフロー環水 循環湯上部投入 凌雲閣大浴場の湯口は二つ。一つは飲泉可能な熱々の源泉。もう一つは、適温の飲めないお湯。そりゃ、もうすぐに分かるよね。後者は低い位置に設けられており、エアロゾルの発生を少なくしようとの意図が感じられて好ましい。 また、ダンナによると男湯ではオーバーフロー環水がおこなわれていて、浴槽へりに溝が切ってあるのだそうだ。あわてて撮ってきた写真を確認すると、やはり小さな女湯にはない。 それでも、匂いといい、お味といい、存在感は十分だ。 |
|||||||||||||||||||||
| 松之山温泉 鷹の湯 |
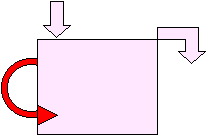 ioc#112 ioc#112源泉上部投入 オーバーフロー 循環湯側壁吐出 松之山温泉はジオプレッシャー型に分類されるという。ということは、いつかは涸れる。湯量も細ってきているようだ。この温泉地を代表する共同浴場「鷹の湯」からして、お湯の供給が追いつかないのだろうか? 飲泉可能・オーバーフローのこの形式は、それこそ、聞いてみなくちゃ分からない。ちなみに、小さな露天は循環なしの源泉そのまま。 |
|||||||||||||||||||||
| 燕温泉 樺太館 |
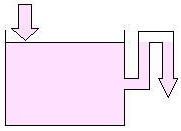 ioc#120 ioc#120源泉上部投入 バスカルの穴より大気圧にて自然排湯 循環なし ちょっと見に、循環かと思ったのがこの形式。ところが、樺太館は源泉掛け流しで、パスカルの穴に危うくだまされるところだった。 洗い場で転ばないようにとの配慮から、この形式にしているそうだ。しかし、湯面に浮かぶ皮脂・毛髪類が洗い出されることがないので、一考を要するところ。 |
|||||||||||||||||||||
| 草津温泉 日新館 |
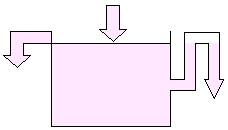 ioc#130 ioc#130源泉上部投入 オーバーフロー+バスカルの穴より大気圧にて自然排湯 循環なし こんなに凝った造りをもつのが草津温泉最古のお宿、日新館。代々、湯守を務めてきたという。「パスカルの穴」なるものを教えてくれた、ワタシにとっては特筆すべきお風呂。 浴槽内に上下方向の新たなお湯の流れをつくり、お湯の入れ替えの促進を図っているそうだ。 |
|||||||||||||||||||||
| 蔦温泉 蔦温泉旅館 |
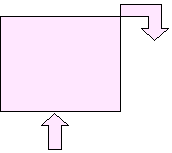 ioc#210 ioc#210底部湧出源泉 オーバーフロー 循環なし 底部から湧き出すお湯に豪快さこそ感じることはないのだが、新鮮なお湯にこだわるならば、このタイプに勝るものなし。何しろパイプでお湯を引っ張りまわしていないのだから。 底部は玉砂利・板・岩盤といくつかある。足裏のツボを押さえているようで、玉砂利の鶴の湯露天もよいのだけれど、造りとしては、やっぱり板敷きの蔦温泉の方が好き。 |
|||||||||||||||||||||
| 明治温泉 | 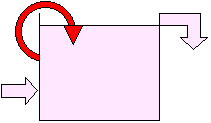 ioc#211 ioc#211源泉浴槽内投入 オーバーフロー 循環湯上部投入 「大浴場のお湯は濾過しているので透明です」との表示に、何やらうさん臭いものを嗅ぎとった。 冷鉱泉なので、加熱した上、濾過だけおこなっているとは信じられないでしょ? 浴槽内を調べてみると、底部の正方形のスリットから、コンスタントにお湯が吸引されている。壁面の穴付近だけ茶褐色。ここから源泉投入されており、ずいぶん冷たい。 |
|||||||||||||||||||||
| 甲子温泉 大黒屋 |
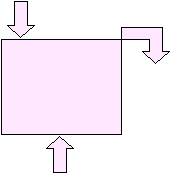 ioc#310 ioc#310源泉上部投入+底部湧出源泉 オーバーフロー 循環なし 一番風呂はなぜ温まらない? 何かの本で読んだのだけど、熱い湯玉とめるい湯玉が混在し、湯温が均等化していないからとか。熱い湯玉で熱さを感じ、その実、身体が受け取る熱量は少ないというもの。ひょっとすると、とがった感じのするお湯も、こんなところに一因あるかも知れないね。 ということは、底部からのお湯の流れを追加したなら、湯温の均等化が促進されてよさそう、あるいは悪そう。どっちなんだろ? ちなみに、甲子温泉では、底部から湯温低めの温泉が湧き出していた。 |
|||||||||||||||||||||
| エピローグ ●湯守のおじさんをよく見かけた関東の温泉 ・那須湯本温泉「鹿の湯」 ・奥鬼怒温泉郷「加仁湯」 ・芦之湯温泉「松坂屋本店」 他 ●ioc#分類テータ(整理中) |
源泉掛け流しの温泉宿をひたすら求めて通っていたので、循環風呂はあまり知らない。というのは決して正しくないだろう。カルキ臭かったり、アンモニア臭かったりして、書く気になれなかっただけのこと。 |
|||||||||||||||||||||
| ▲Top |
||||||||||||||||||||||
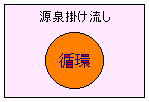 さてと、巷間、温泉の種類としては、「源泉掛け流し」と「循環」の2つに大別されてはいるものの、実際、いろんなお風呂に浸かってみると、その狭間にはさまざまな様式がある。
さてと、巷間、温泉の種類としては、「源泉掛け流し」と「循環」の2つに大別されてはいるものの、実際、いろんなお風呂に浸かってみると、その狭間にはさまざまな様式がある。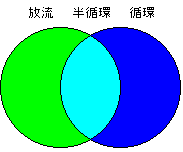 「源泉」という実質を排除して、形式だけに特化してみる。「循環」も「掛け流し」も、いずれもお湯の「IN」と「OUT」の形式だけを表す言葉。
「源泉」という実質を排除して、形式だけに特化してみる。「循環」も「掛け流し」も、いずれもお湯の「IN」と「OUT」の形式だけを表す言葉。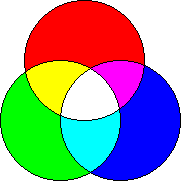 そこで今回、浴槽まわりのお湯遣いとして、次の3本柱を立ててみた。
そこで今回、浴槽まわりのお湯遣いとして、次の3本柱を立ててみた。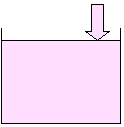 源泉の生い立ちにもいろいろあって、
源泉の生い立ちにもいろいろあって、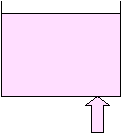
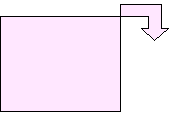 滝のように流れ落ちるお湯の豪快さは、もとより捨てがたい。しかし、ひたひたと湯船のふちからあふれ出す、そのひっそりとした営みにこそ、安らぎのひとときを覚えてしまう。ワタシも枯れてきたかな〜。
滝のように流れ落ちるお湯の豪快さは、もとより捨てがたい。しかし、ひたひたと湯船のふちからあふれ出す、そのひっそりとした営みにこそ、安らぎのひとときを覚えてしまう。ワタシも枯れてきたかな〜。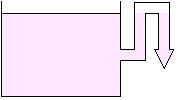
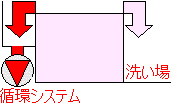 前者は湯船のふちに側溝が切られており、ところどころに集水用の穴が開いている。はじめて見たときには「パスカルの穴」かと思ったが、循環用の穴だった。はっきり記憶しているのは塩原温泉「
前者は湯船のふちに側溝が切られており、ところどころに集水用の穴が開いている。はじめて見たときには「パスカルの穴」かと思ったが、循環用の穴だった。はっきり記憶しているのは塩原温泉「