| わがまま温泉日記 | お風呂の科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲当世レジオネラ考 ▲源泉かけ流しと循環 ■ ▼泉源から湯船まで ▼温泉法 vs 公衆浴場法 |
〜源泉かけ流しのお湯を塩素消毒〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩素消毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●論理命題 命題・我思う故に我あり というのは観念論で有名なデカルトの命題。 逆・我あり故に我思う という命題は唯物論というんだそうだ。 では、完全一致する命題といえば 命題・私は私である 実にエゴイスティックなようでいて、一面の真理を突いているかも知れないな。中島みゆきの歌に「かもめはかもめ」なんてのも。 ●人数が多いから塩素消毒? しばらく、温泉とは離れていたので、随分、そちらの情報にも疎くなっている。 先日来、いろんな情報を集めてみるに、こりゃ、驚いた。 外界から人間様が持ち込むレジオネラ菌はお湯の中では増殖しないはずだから、湯船の中でのコロニー数は人数に比例すると考えてよい。 しかるに、バイオフィルムの中では幾何級数的に増殖が繰り返される。そして、事故の起きそうな施設でのコロニー数は指数レベルであることを忘れてはならない。 そもそも、源泉かけ流したるもの、換水率が高ければ、レジオネラ菌だってお湯と一緒に掛け流し。 |
とうとう道後温泉本館にも塩素が投入されたやに聞く。道後温泉といえば有馬・白浜と並び立つわが国三大古湯の一つ。草津はどうだ、玉川は? ということになるのだろうが、如何せん、大和朝廷創世紀のその頃は、残念ながら蝦夷地であったにちがいない。なにしろ、ことの記述は奈良時代の日本書紀にあるというから。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法の網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●公共の福祉 法律書なんぞ読んでみると学説あれこれ、かしましい。 ・外在的制約説 ・二元説 ・内在的制約説 ●距離制限 経済的自由の侵害ということで、薬局・酒屋・銭湯と、憲法判断も多数なされているようだ。 A.消極目的規制 B.積極目的規制 と二分した上で憲法判断がなされるというのが単純な理解。銭湯のユニークなところといったら、AからBへとカテゴリーが移ったことだろう。 お風呂は時代を映す鏡なのだ。 |
わが国は世界に冠たる法治国家を誇るだけに、許認可のあまりの多さに規制緩和の外圧すらかかるありさま。そして、許認可を得るということは、行政機関の指導監督に服さなくてはならないことを意味するが、補助金も貰ってないのにナゼじゃ〜という悲痛な叫びが聞こえて来るのも頷ける。
しかし、これらの施設が1本の法の枠に収まっているはずもなく、一応の分類なんていうのは成されてはいる。まずは、公衆浴場と、旅館の2つに大別できる。前者が公衆浴場法、後者が旅館業法の規制を受ける。公衆浴場は、さらに2つに枝分かれする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉関連法令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まずは、温泉に関する現行法令を調べ得る限りで調べてみると、次の通り数は少ない。もちろん、民法の分野では、信義則・公序良俗と並ぶ一般原則、なにしろ民法1条権利濫用にまつわる「宇奈月温泉事件」が判例として確固たる地位を占めてはいるが。
以上の法令、どこをどう読んだところで、「温泉に塩素を投入しなさい」なんてこと、これっぽっちも書いてはいない。ましてや、日本国憲法に「温泉」の文字を見つけることなど到底できない。ということは、法体系が命ずるところ、温泉に浸かるなんていう些細なことは、どんどん下位の法規に命令委任しておけばよいという認識でしかない。こりゃ、条例レベルにまで、下りていかなきゃならないな。
見つかったのはいいけれど、ここでもやはり、法律→告示のお決まりパターン。法律→告示→条例と、どんどん身近に下りてくるはず。そもそも、都道府県ごとに対応が異なるということは、やっぱり条例レベルの問題。さっそく、調べてみなくちゃならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●自由権の侵害 本来、自由であったはずの行為を法で縛るということは、人権の制約に直結しかねない。だからこそ、内容として謙抑的、形式として民主的な手続きを経なけりゃならない。 しかし、民主的な条例が行政機関の下位に位置するこの不思議。 ●条例の位置付け これにも学説いろいろあるが、法令以下という点では一致している。しかし、法令の範囲をどう捉えるかで結果が変わる。 面白いのは、国家の法体系と地方の法体系は次元が異なり、上下の差なんてつけられないという説。 いろんな人がいるんだね〜。 |
ワタシの暮らす地域には「ポイ捨て禁止条例」なるものがある。歩きタバコはしないから、全く無縁の条例だけど、唯一これ以外には馴染みの条例なんか知らないんだね。
条例というのが、地方議会がつくった自主的法規であることくらいはワタシだって知っている。だから、その地理的適用範囲は当該自治体に限られる。この限りではアメリカの州法と同じだ。しかし、その条例がわが国の法体系の上で、いかなる位置付けを得ているものやら分からない。調べてみると、右のような序列になっているみたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題の所在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●参考文献 元厚生官僚 宮本政於氏による暴露本(講談社) ・お役所の掟 ・お役所のご法度 ●違憲訴訟 憲法13条に基づいた幸福追求権の一つとして、有名なのが環境権やら知る権利。 源泉かけ流し温泉に浸かる権利などという新たな権利を、基本的人権として主張するなんてのは愚の骨頂。法律上の主張に事欠き、最後は憲法上の主張に至る。これって、窮地に陥ったとき、法廷で主張する最後の最後の手段だという。 何でもかんでも権利として主張すればよいものでもないらしい。 |
温泉への塩素投入につき、法律上の規制はない。告示にはある。しかし、告示をもって、法的拘束力を備えた法規範と捉えてはならない。なぜなら、告示は一介の行政上の勧告にしか過ぎないのだから。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条例の評価基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●行政指導 法規が多少時代遅れになったにせよ、迅速な措置が取れるというのは行政指導に負うところが大。立法・司法の判断には時間がかかる。さらには、微に入り細を穿ったものとはなり難い。 その限りでは有用性も認めるが、行政指導が実質的な法規となってはかなわないな〜。 だって、行政処分ではないだけに、司法審査の対象にはならないのだからタチ悪い。 文書にせよ、口頭にせよ、「営業許可を取り消すぞ〜」と脅されりゃ、ヤクザだってビビッて帰る。 |
それにしても、都道府県の各地において、塩素消毒に対する取り組み方の違いはどこに起因するのだろう。あれこれ、思いつくままに想像をめぐらせてはみたのだが、次の2点に集約されそう。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛県条例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●たわごと 形式面を見るだけでも、条文の出来の悪さは驚くばかり。こんなのが、まかり通っているのかね〜。 法整合性なんてこと、思いも及ばぬことらしい。あら探しをすれば、矛盾はたくさん見つかるだろう。 それより何より問題は、規制条項を追加的に増やしていくと、どんどん県民の自由の幅を狭めているのに気づかないのかな? しかる後、例外規定で声の大きい議員の利権を守るというパターンに陥らざるを得ないことに気づかないのかな? やはり、吏員たるもの、プライドもって、きちんとした条例原案を示すべきなのである。 ●条例の改廃請求 地方自治法74条に定めはあるが、有権者の50分の1もの署名を集めなくてはならない。 |
ことの発端は、源泉かけ流しの道後温泉本館の湯に、塩素が投入されたというところにある。こんな動きが日本全国津々浦々にまで広がったのではたまらないから一気に関心が高まったんだろうね。でも、金田誠一議員のせっかくの質問(どこかで見かけたんだけど行方不明)だって、あまり要領を得たものとはいえなかったな〜。向こうもこっちも、どっちもどっち・・・。 ●公衆浴場設置等の基準等に関する条例(改正平成15年7月18日条例第46号)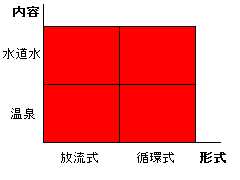 第5条 公衆浴場の管理は、次に定めるところによらなければならない。
(13) 浴槽水は、塩素系薬剤を使用して消毒し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常1リットル中0.2ミリグラム以上0.4ミリグラム以下とし、かつ、最大1リットル中1.0ミリグラムを超えないよう努めるとともに、当該測定結果を検査の日から3年間保存すること。ただし、浴槽水の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、浴槽水の水素イオン濃度指数(pH)が高くこの基準を適用することが不適切な場合又は他の消毒方法を使用する場合であつて、他の適切な衛生措置を講ずるときは、この限りでない。 (19) 回収槽(浴槽からあふれ出た湯水を配管により回収するための水槽をいう。以下同じ。)の湯水を浴用に供しないこと。ただし、回収槽の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌その他の病原菌が繁殖しないよう回収槽内の湯水の塩素消毒等を行う場合は、この限りでない。 第5条本文と組み合わせた上で13項(号?)を読むなら、「公衆浴場における浴槽水の管理には塩素系薬剤を用いなさい」というのが原則だ。但書で除外規定はついてはいるが、お湯の実質に配慮したものであって、放流式・循環式といった形式面への配慮はいささかもない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都条例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●条文の読みにくさ 法律の条文も憲法くらいならまだしも、行政法規ともなると、これほどの悪文がこの世にあろうかというくらい、無味乾燥な単語の数々が、又は・且つなどという接続詞により延々続く。 しかし、それも規制の網を場合分けをおこないながら慎重にかけていこうという趣旨。同情こそすれ、長いだの悪文だのと非難する気になれなくなるから不思議だね。 裏を返せば簡略すぎる条文は一網打尽法案なのかも知れないな。 ●都道府県条例 調べるには、 ・都道府県名 ・条例集 or 条規集 と打ち込んで、検索してみて下さいな。 |
続いて、源泉かけながしとは、ほど遠い雰囲気をもつ東京都による規制はどうかな。さぞや塩素ブチ込み酷たらしいことになっているかに思いきや、あれれ〜! 源泉かけ流しのお湯を塩素消毒せよとはなってはいない。 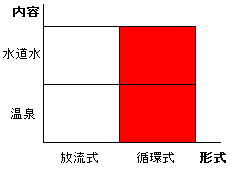 第三条 法第三条第二項の規定による条例で定める措置の基準のうち、普通公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。 第三条 法第三条第二項の規定による条例で定める措置の基準のうち、普通公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。・八の三 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講じること。
・・ニ 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が一リットルにつき〇・四ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用し、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。
端的に言えば、放流式あるいは循環式という形式面からの場合分けをなしたところに尽きるのだ。すなわち、第3条8項の3「循環させるときは」と条件をつけ、それを受けた形で、同ニ号「塩素系薬剤」という規制をおこなう形になっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境省の動き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●環境省 環境行政の歩み 1971 公害対策本部を発展的に解消し、総理府の外局として環境庁設置 2000 省庁再編により環境省となる |
温泉法はもとは厚生省の所管であった。なにしろ環境省なんてお役所自体、なかったのだから。そのせいか、条文上は、厚労省と随分きわどく重なる部分があるんだね。秘湯系、すなわち国立公園内に宿をとることの多いのワタシとしては、環境省にその管理を委ねたいところであるが、保健所のような出先機関を張り巡らしてはいないところに、それを望むのは無理っていうもの。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピローグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ワタシが愛してやまない温泉が「マワシ・ヌルメ・ワカシ」なしの自噴温泉であることは、ホームページの基本姿勢として一貫、貫き通してきたポリシーでもある。せっかくの味わい深い温泉が塩素まみれになってはかなわない。厚労省のお役人のみならず、愛媛県議会の議員の皆さん、ひいてはそうした代表を選んだ県民に至るまで、温泉の「風味」というものをご存知なきやに思えてしまうのが悲しい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲Top |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
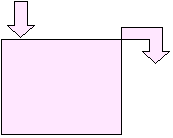 由緒正しき温泉に塩素が投入されたからといって騒ぐのではない。機械文明の進んだ当世だからこそ、こんな悩みも抱えてしまう。すなわち、温泉の浴槽内での利用法につき、大きく分けて次なる2種が厳然として存在するにも関わらず、双方に同じ処方で立ち向かおうという動きがあるのだ。
由緒正しき温泉に塩素が投入されたからといって騒ぐのではない。機械文明の進んだ当世だからこそ、こんな悩みも抱えてしまう。すなわち、温泉の浴槽内での利用法につき、大きく分けて次なる2種が厳然として存在するにも関わらず、双方に同じ処方で立ち向かおうという動きがあるのだ。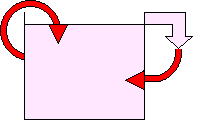 掛け流し→
掛け流し→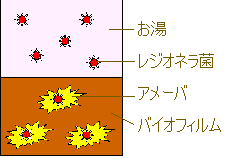 毎日換水、毎日清掃、これ基本。バイオフィルム(生物膜)だって、循環構造では難しいけれど、掛け流し浴槽では簡単に清掃除去できる。つまり、清掃の手間と、その間の身入りを惜しむな! ということなんだね。だとすると、掛け流しの温泉に、塩素消毒は要らない。
毎日換水、毎日清掃、これ基本。バイオフィルム(生物膜)だって、循環構造では難しいけれど、掛け流し浴槽では簡単に清掃除去できる。つまり、清掃の手間と、その間の身入りを惜しむな! ということなんだね。だとすると、掛け流しの温泉に、塩素消毒は要らない。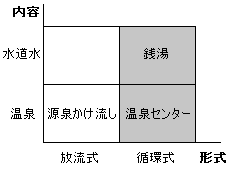 ここでは、条例の内容をチェックしてみたいと思うが、その前に評価基準が必要だ。長さを測るには物差しが必要でしょ。
ここでは、条例の内容をチェックしてみたいと思うが、その前に評価基準が必要だ。長さを測るには物差しが必要でしょ。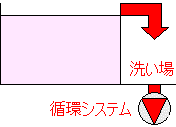 もっと驚いたのが19項但書だ。回収槽の湯水を再使用してよいことが謳われている。よもや、あのおぞましい循環システムのことではあるまいな。
もっと驚いたのが19項但書だ。回収槽の湯水を再使用してよいことが謳われている。よもや、あのおぞましい循環システムのことではあるまいな。