コシャマインの戦い
注文された小刀の出来ばえをめぐって、和人の鍛冶屋がアイヌの少年を殺した事をきっかけに、 コシャマインの率いるアイヌ軍が(1457年)和人の武将達の居館を襲い、そのほとんどを落としましたが、 松前藩の始祖とされる武田 信広の策略によってコシャマインが討たれアイヌ軍は敗北しました。

これはアイヌの家でチセ。(平取町二風谷に復元)
アイヌの人々は本来は松前藩を中心とする和人と対等な交易関係を結んでいた。
商場では和人とアイヌとの交歓儀礼(オムシャ)が行われ、米・タバコ・衣類・鍋などの
鉄製品その他本州からの物産と、アイヌの生産物である干鮭(からさけ)や熊・鹿の皮、
鷲の羽根などが交換された。 しかし、和人たちはしだいに交易関係を一方的にゆがめていった。
アイヌ勘定と言う言葉は和人による数の数え方のごまかしを表したものである。
もっと鮮明な例は夷俵(えぞたわら)で干鮭百本に対して米一俵と言う決まりがあったが
、その俵は普通の俵の半分のニ斗入りだった。
それがさらに江戸時代の後期になると
八升入りを一俵と称するようになった。交換
比率だけでなく商場が各地に設定され和人の力が
及んできて鷹や砂金を採りに和人が入り込んで来ると和人との交換が拡大してきて、それを
前提とした生活様式が固定化してくると、その他さまざまな影響がアイヌ社会に及び、アイヌ
の人々の生活は動揺した。
 |
 | アイヌの人々の遺跡として、現在見る事の出来る主なものはチャシである。静内町には 江戸時代の初期に起こった有名なシャクシャインの蜂起(1669年)のさいにシャクシャイン達が立てこも ったシベチャリ(静内の古称)のチャシ(砦) 跡が残っている。 現在はシャクシャインの像もここに建てられている。 この蜂起は前記のようなアイヌ社会 への圧迫に対する大規模な反撃だったが、それが松前藩に鎮圧されてからは、アイヌの人々 への和人の支配はいっそう強くなった。 |
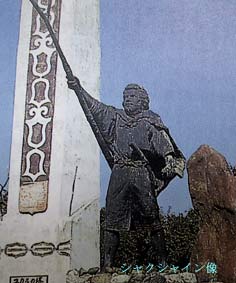 |
シャクシャインの戦いの後、クナシリ・メナシの戦いが(1789年)江戸時代後期、場所請負人
(松前藩が財政維持のため蝦夷地を分割し家臣に知行としてアイヌとの交易を認めた。)
らの横暴に耐えかねてクナシリ(国後島)メナシ(北海道東部)地方のアイヌ達が立ち上がった
ものの、松前藩に制圧され38名のアイヌが処刑されこの後アイヌ側の組織だった抵抗は
最後になる。 アイヌの蜂起による蝦夷地統治の不安と、ロシア人の接近に触発されて幕府は一時期蝦夷地を 松前藩より取り上げて直轄した。十八世紀末〜十九世紀の始めにかけて、この時、東蝦夷地に 幕府が建てた寺が三つあり、 三官寺と称され、有珠の善光寺・厚岸の国泰寺・様似の等樹院 があり、和人には死後の安らぎを与え、アイヌには教化と同化を勧める教えを勤める 任務をもっていた。歴史的にも価値の高いもので北海道三古刹として、今も現存している。 |


1845年(弘化2年)3月2日松浦武四郎(27歳)蝦夷地に渡るために江戸を出発、旅人の取締りが
厳しいため江差の人別に加わり、和賀屋孫兵衛の手代と言う事にして東蝦夷地に入り、シレトコ岬
を回って10月頃箱館にもどる。松浦武四郎この年から6回にわたり蝦夷地を探検、
虐げられたアイヌの生活を記録。
1853年(嘉永6年)6月3日黒船、ペリー浦賀に来航、6月12日明春の再来を約して去る。
7月18日ロシヤ使節プチャーチン長崎に来航、8月19日長崎奉行、大沢豊後守に国書を手交して、
国交及びカラフト千島の境界画定を要求。
安政・万延・文久・慶応・・・明治維新まで14年・・・1868年明治元年・・・続く・・・


「アイヌ民族を理解するために」を引用させて頂きました。
北海道出版企画センター発行
榊原正文氏著 「武四郎千島日誌」を引用させて頂きました。
写真19・22「北海道開拓記念館」蔵複製