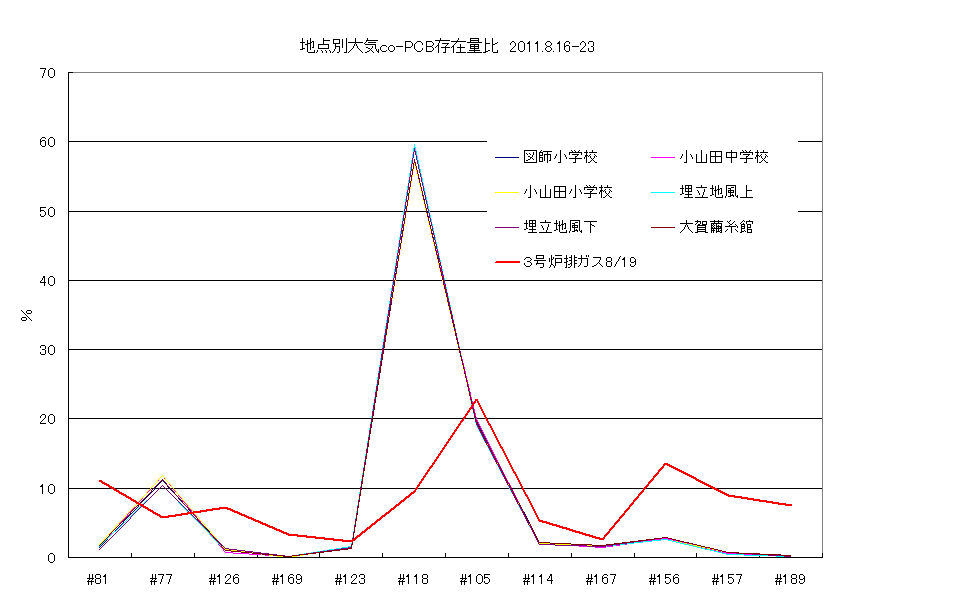リサイクル文化センター
周辺大気のダイオキシン調査
(2002年6月~2011年10月測定分)
◆ダイオキシン類とは、ポリ塩化ダイベンゾパラダイオキシン(PCDDs:通称ダイオキシン)、ポリ塩化ダイベンゾフラン(PCDFs:通称ジベンゾフラン)、及びコプラナーPCB(PCBs)です。なお、町田市でコプラナーPCBが測定対象となったのは1999年度からです。
・町田市では、リサイクル文化センター周辺の、小山田小学校、小山田中学校、少年野球場、大賀繭糸館、埋立処分場(風上・風下)、の各地点で、継続して大気中のダイオキシン類の調査を行っています。調査は7日間かけて行われます。(以前は2日間の測定でした。このデータはtopix30へ)
・以前の調査データに基づく分析は、主にダイオキシン(PCDDs)およびジベンゾフラン(PCDFs)の異性体についてでしたが、今回はダイオキシン類の一群であるコプラナーPCBに着目しました。
・コプラナーPCBは、他のダイオキシン類(2,3,7,8、-TeCDDや1,2,3,7,8、-TeCDD)と比べれば毒性は低いものの、環境中の存在量は桁違いに多く、1998年の厚生省の調査(食品からのダイオキシンの1日摂取量調査)によれば、日本人が1日に摂取するダイオキシン類の総量の内、約6割をコプラナーPCBが占めています。
・また、コプラナーPCBの12種の異性体(毒性等価係数のあるもの)の内、#77(non-ortho体)、#105、#118(mono-ortho体)は、環境中のコプラナーPCB濃度の約8割をしめています(同環境省調査)。
●初めに、ダイオキシン類の総量で、地点ごとの経年変化を見てみましょう。夏の値が高く、冬の値が低い傾向を繰り返しながら、だんだん値が全体に低下してきている事が判ります。
しかし、2009年8月からは振幅の幅が広がる傾向にあるのが判り,2010年6月では、小山田小学校、中学校共に、これまでの最高値をしめしています。2011年の計測では、また低下傾向にあります。

●次に、測定日毎の地点別のダイオキシン類の同属体の値を、最新の2011年8月と10月のデータでみてみましょう。
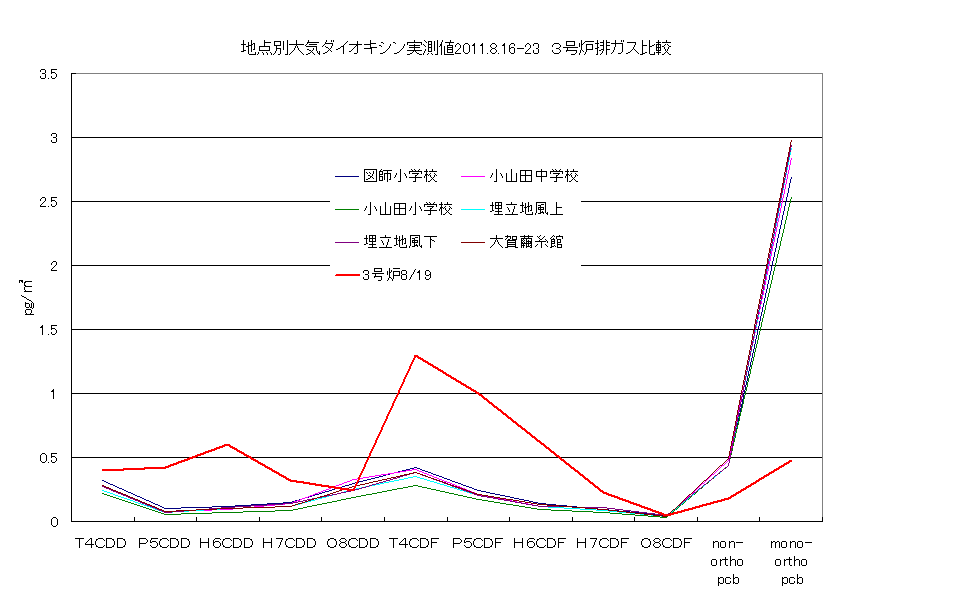
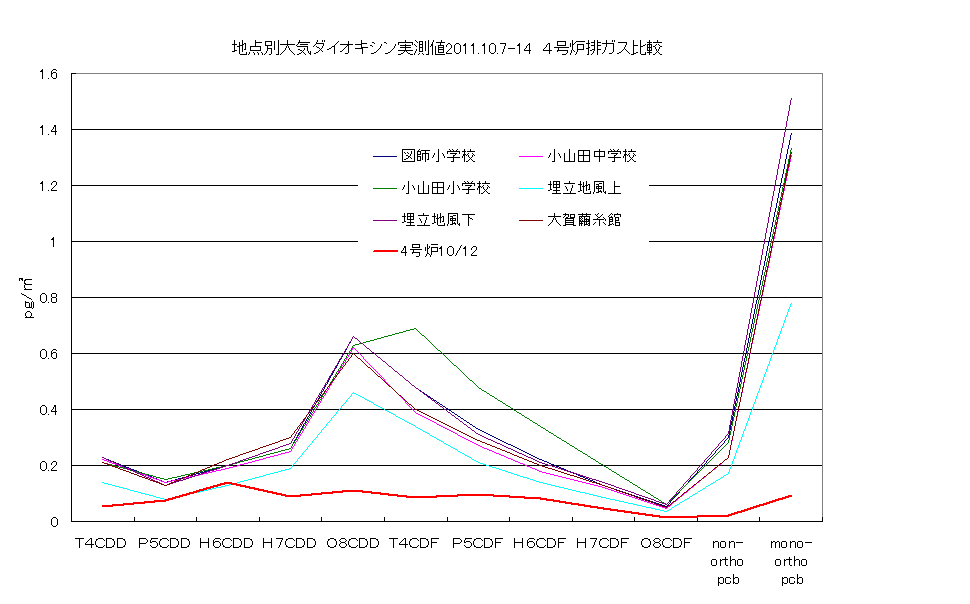
●次に、排ガスの影響を見るため、同族体の組成比をグラフ化してみました。赤線が排ガスの値です。
どちらのデータでも排ガスと大気の組成は異なることが解ります。
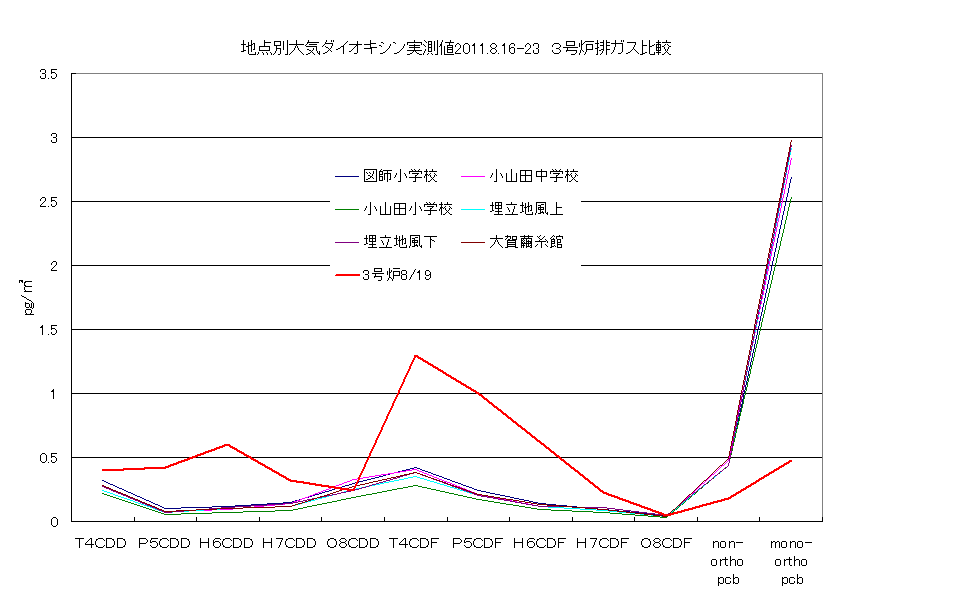
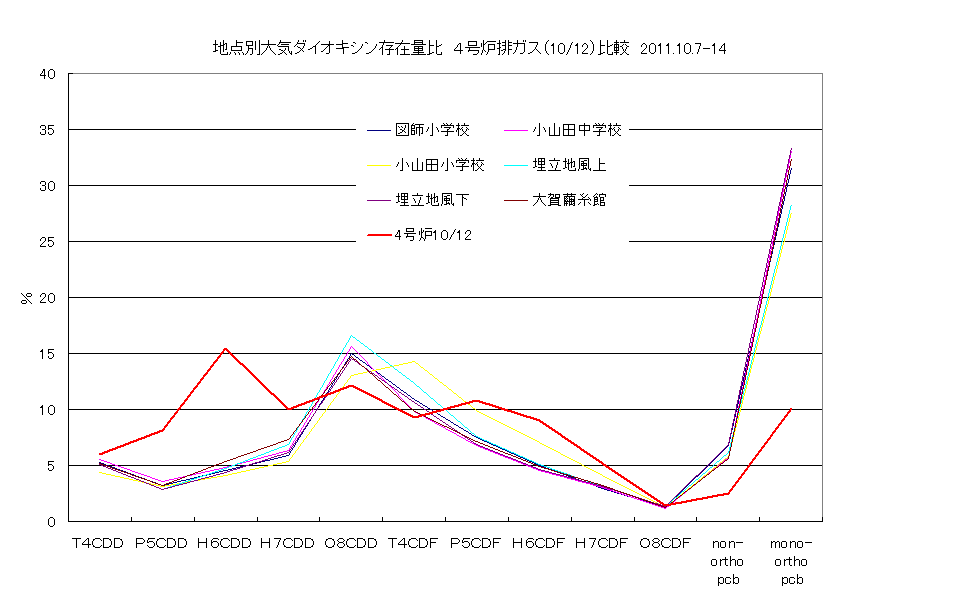
●さらに、コプラナーPCBの組成を比較してみました。赤の線が排ガスの組成比(実測値存在量比)ですが、周辺大気の組成分布とは2008年2009年のデータでは明らかに異なることが解ります。このことから、焼却炉からの排ガスの影響は少ないと思われます。
※2010年1月のデータでは、やや近似していることが分かりますが、最新の2011年6月のデータでは#118の割合が約15%と下がり、2008~2009年のデータと同様に他の6地点とは異なる分布をしめしています。
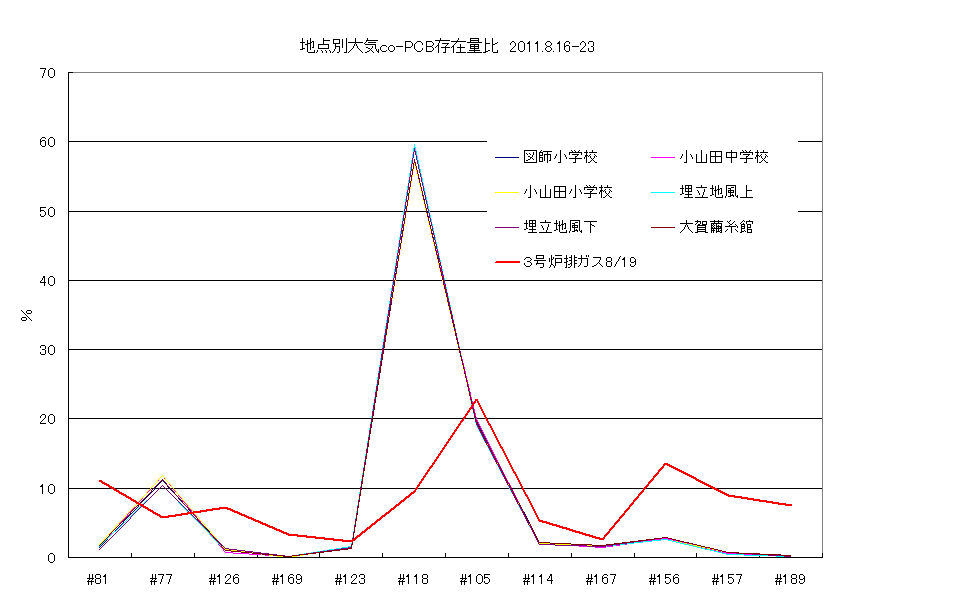

●では次に、コプラナーPCBの異性体の値を、地点毎にその経年変化を見てみましょう。
#118>#105>#77の順に異性体の時系列の変化が大きく、その他の異性体は変化が小さい事が判ります。そして、高低を繰り返しながら段々と値が低下してきていることが判ります。夏季は高く、冬季は低いという傾向です。2010年6月のデータが、各地点で高い傾向を示しています。特に図師小学校を除くデータでは突出しているのが気になります。
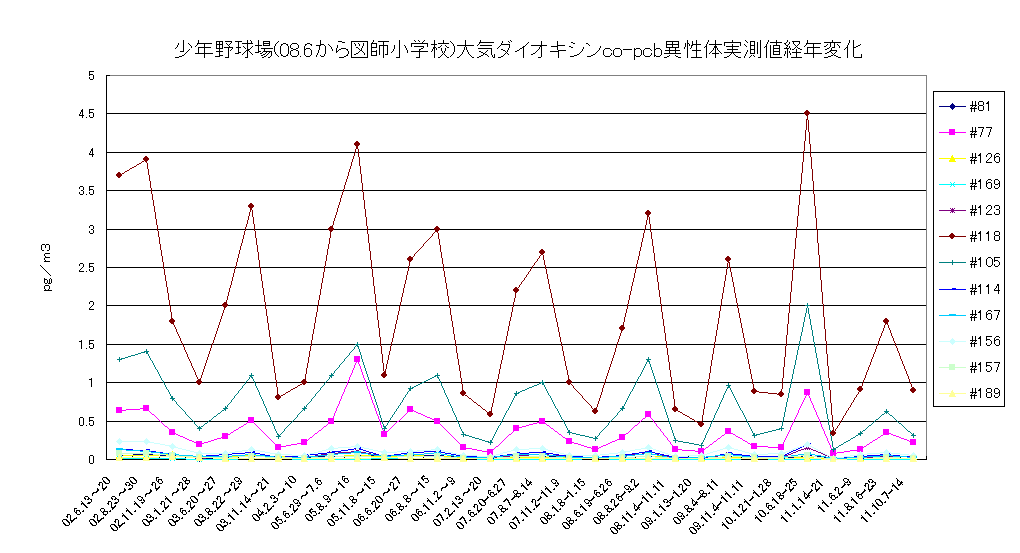
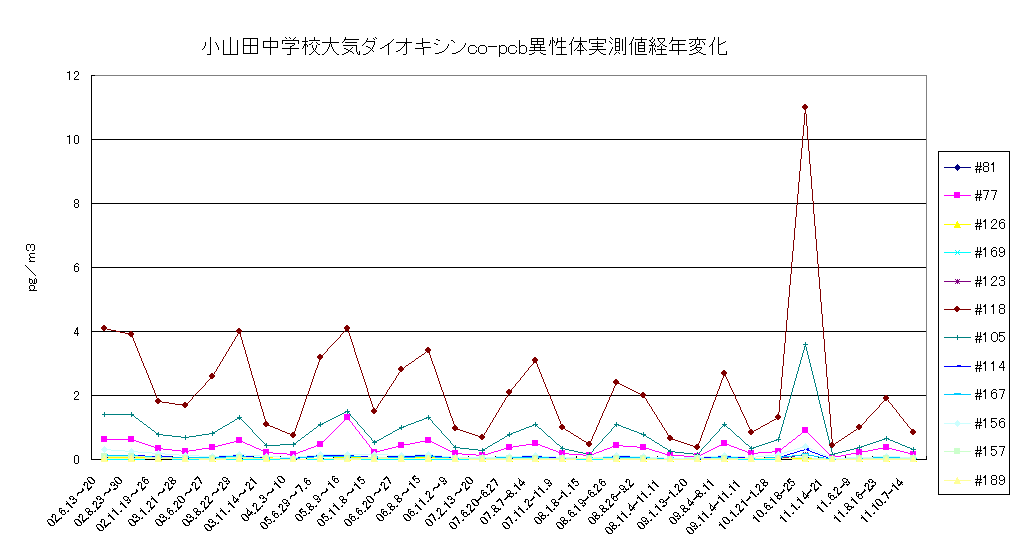
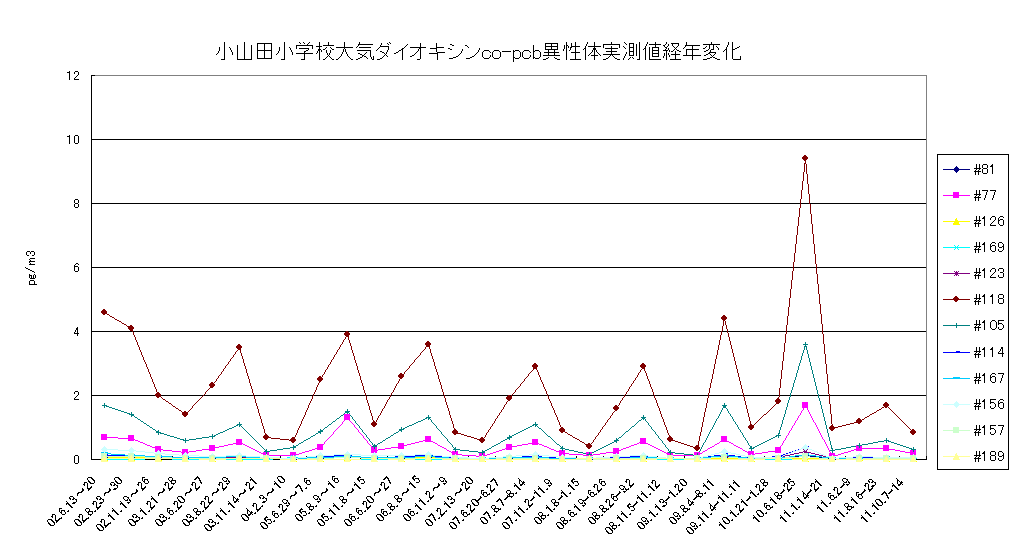
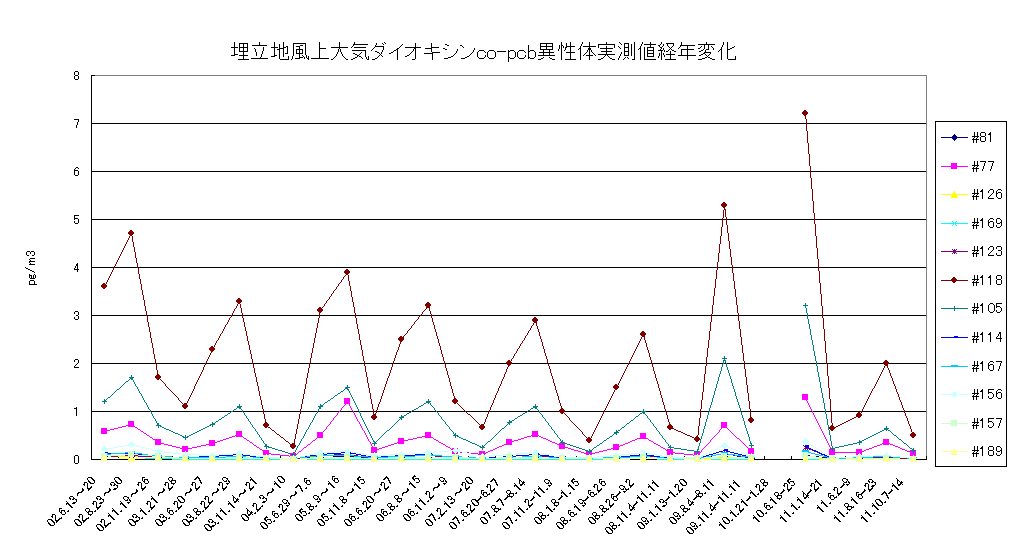
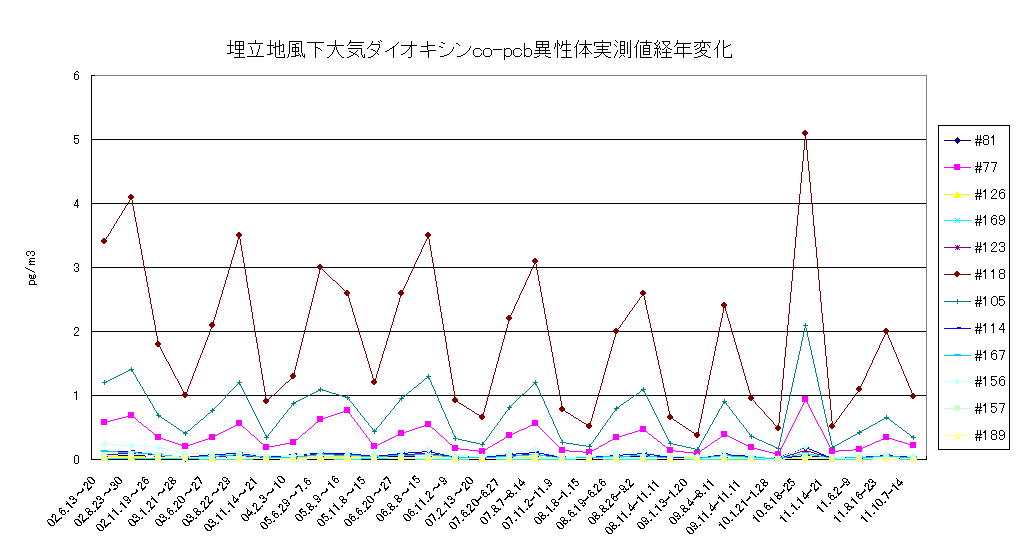
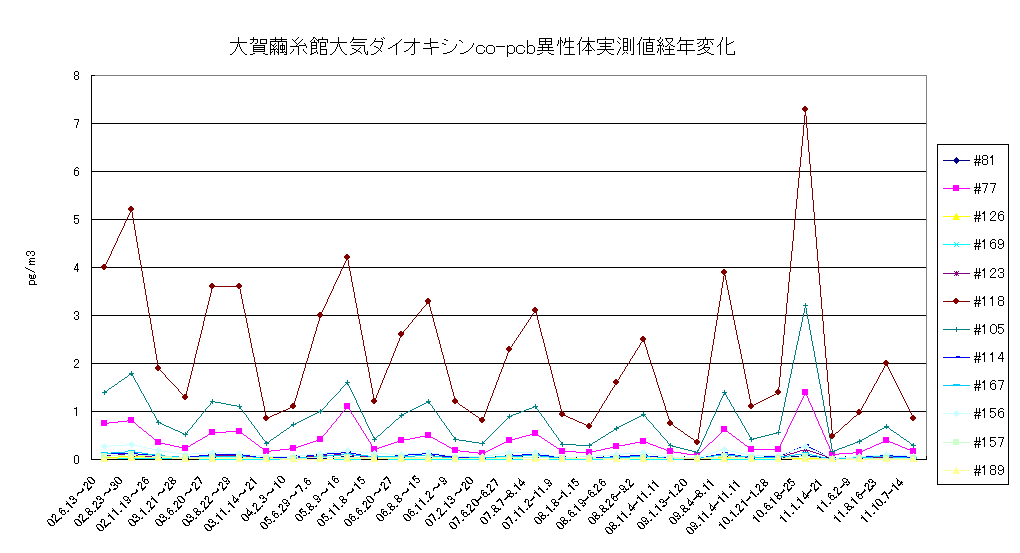
●最後に、コプラナーPCBの異性体の存在量の比較を見てみましょう。
最新の2010年8月と10月の測定データをグラフ化したものですが、#118が約50~60%、#105が約20~30%、#77が約10%という構成になっているのが判ります。地点による大きな変化は見えられません。また、燃焼に由来するといわれる#169や#126の割合は低くなっています。
この傾向は、市役所や鶴間会館、小山センターで測定されている大気のダイオキシン類調査のコプラナーPCBの存在量と同じ傾向を示しています。(ただ、ダイオキシン類全体で見ると、市役所の値だけがmono-orthoPCBの存在量が突出していますので、一般的な傾向とは違う、別の要因が加わったものと思われます)