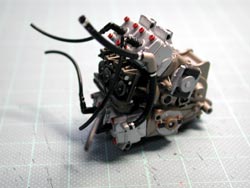|
まずはいつもの通りカウル類の整形から始めます。 キットナンバー自体は比較的新しい部類のキットですが、いかんせん金型が’84年(だったかな?)と古いキットです。 最近の金型を使用したキットと比べてバリ&ヒケの嵐です。。。 写真の通り、合わせ目を中心にパテを盛りまくります。 整形で時間がかかるのは覚悟の上ですが、気が重いなぁ・・・。(^_^;) カウルパーツのアンダーカウル部分は接着後、裏側から瞬間接着剤で補強しています。 |
  |
これもこの時代のキットの定番作業、チャンバーの裏打ちです。 まずはポリパテで全体を埋めて、おおまかに整形します。 きちんと埋めたつもりでもパテを盛っている段階で気泡が入ってしまっています。 そういう気泡のような小さいものはポリパテを使わず、タミヤパテで埋めてしまいます。 ポリパテでも問題ないのでしょうが、なんとなくこういう小さな傷などを埋めるにはタミヤパテの方があってるような気がするので・・・。 ちなみに技術的な根拠はまったくありません。(^_^;) |
 |
整形中のアッパーカウルです。 カウルステーが出てくるセンターの穴は埋めてしまいました。 後でカウルステーを加工して、虫ピンでカウルを留めるようにします。 ナックルガードもこの地点で接着してしまいます。 カウル本体との間に隙間が出来るので、パテで埋めて整形。 さすがにこの時代のキットは手ごわいです。 パテ盛り→整形の繰り返しばかりで、なかなかサーフェーサーまで作業が進みません。。。(^_^;) |