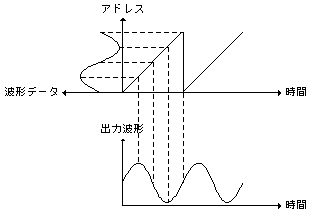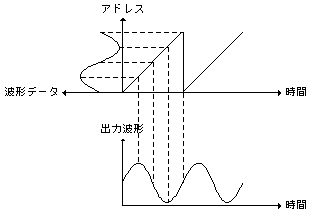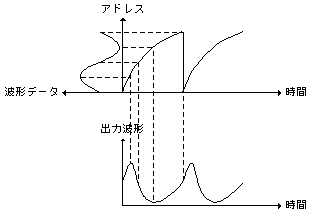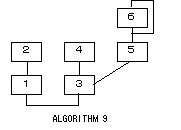3.DX7による音作り
3-1.DX7の内部構造
DX7では2章で説明した「キャリア」「モジュレータ」となるオシレータ(発振器)を持っています。これをオペレータと呼んでいます。発振器とは言ってもDX7はデジタルシンセですからアナログな発振器を持っているわけではなく、内部のメモリ上に波形テーブル(正弦波テーブル)を記憶しています(左図の左上の部分です。図を時計回りに90度回転させてみると分かり易いと思います)。
さらにこれとは別に上記波形メモリ上のアドレスと時間を軸としたノコギリ波(変調がかかってない場合)を持っていて、時間軸上のある時間にのアドレスに対応する波形テーブル上の値を読み出すことにより正弦波が出力されます(下図の右半分)。
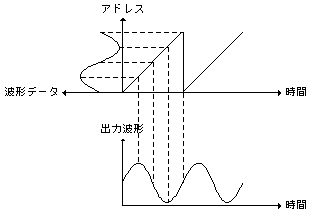
モジュレータを使って変調をかけると、このノコギリ波の波形が変化し、読み出す波形メモリのアドレスが変わるため出力波形は複雑なものとなります(下図)。
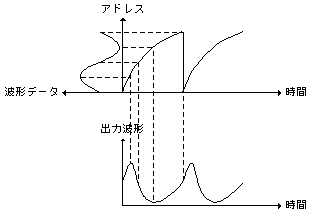
また、各オシレータは出力部にエンベロープジェネレータと出力レベル調整部を持ち、波形の全体的なレベルを調整することが出来ます。
3-2.オペレータ
DX7の場合は6つのオペレータを持ち(DX7の弟分のDX21やV50などは4つです)、このオペレータを直列、並列に組み合わせて音を作っていきます。直列に繋いだ場合は上のオペレータ(B)がモジュレータ、下(A)がキャリアになります。並列の場合はA、Bともキャリアとなり、出力は加算合成された波形となります。
 前節でオシレータはレベルコントロールができると書きましたが、キャリアとモジュレータではどのような違いがあらわれるのでしょうか。
前節でオシレータはレベルコントロールができると書きましたが、キャリアとモジュレータではどのような違いがあらわれるのでしょうか。
キャリアは一番出力に近い部分に位置しているため、レベルコントロールがそのまま音量レベルになります。つまりレベルがゼロになると音は全く出ません。
これに対してモジュレータの場合はキャリアのノコギリ波にのみ影響を及ぼすため、レベルを上げると変調はより強力なものとなり倍音成分が多くなります。逆にレベルをゼロにすると、変調が全くかからなくなりますが、モジュレータが音量レベルに作用しないため音が出なくなるということはありません。
DX7の音色を決めるのにはもう一つ重要な要素があります。それはピッチ(周波数比)です。キャリアに対しては基本周波数に対する周波数比であり、ピッチを2倍にすれば同じキーを押したときの音程は1オクターブ高くなります。モジュレータのピッチの場合は下につながるキャリアに対する周波数比となります。ピッチの決定には整数部(コース)と微調整部(ファイン)があり、これらの組み合わせによって、より複雑な波形を生み出すことが可能です。
但しFM音源の場合はPCM音源とは違って各パラメータの値から最終的な出力波形(音色)を予想することは難しく、経験によって目的の音色を作っていくしかないようです。
3-3.アルゴリズム
前節では直列につながった2つのオペレータを使って音作りについて話を進めましたが、DX7には前述のように6つのオペレータを持っています。これらの組み合わせを「アルゴリズム」と呼びます。DX7の場合はパネル上に書かれた32種類のアルゴリズムを選ぶことができます(下図はその例)。理論的にはこのほかにもいくつものアルゴリズムが考えられますが、DX7では特に音作りに効果的なものを32種類選んでいるようです(SYシリーズなんかだともっと多いです)。
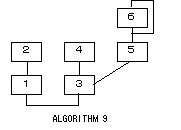
 アルゴリズムの図を見ると、オペレータの1つがループしてるのが見られます。これはフィードバックのかかったオペレータを表します。つまりオペレータのフィードバックレベルの数だけオペレータが直列接続されたものと考えます(下図)。
アルゴリズムの図を見ると、オペレータの1つがループしてるのが見られます。これはフィードバックのかかったオペレータを表します。つまりオペレータのフィードバックレベルの数だけオペレータが直列接続されたものと考えます(下図)。
 一般に倍音成分の多いピアノやブラス系の音は直列多段接続、オルガン系の音は並列接続といったような使い方をします。また、モジュレータの周波数比を2倍にするとシンセリードっぽい音、整数倍以外に設定すると金属的なノイズが得られ、ベルやシンバルなんかの音を作ることができます。
一般に倍音成分の多いピアノやブラス系の音は直列多段接続、オルガン系の音は並列接続といったような使い方をします。また、モジュレータの周波数比を2倍にするとシンセリードっぽい音、整数倍以外に設定すると金属的なノイズが得られ、ベルやシンバルなんかの音を作ることができます。
3-4.エンベロープジェネレータ
各オペレータはエンベロープジェネレータ(Envelope Generator、以下EG)を持ちます。エンベロープとは包絡線、つまり出力レベルの輪郭線(?)とでも言うのでしょうか。キャリアに対しては音量変化、モジュレータに対しては音色変化をさせるために使います。DX7のEGではLevel1〜4、Rate1〜4のパラメータを持ち、Levelは出力のレベル、Rateは変化のスピードを設定します。

3-5.LFO