コハクノバラ
「……もし、私が何か、後悔しているとすれば…」
長い沈黙の後で、サガは遠く虚空を眺めながらぽつりと呟いた。
「…"あの子"をひとりにしてしまったことか……」
その横顔は悔恨と苦悩に満ちているように見えた。
仮面を外してなお仮面のように無表情ないつものサガからは想像もつかない、泣き出しそうなその面差しは、もう長く会わずにいるもうひとりの「サガ」にとてもよく似ていた。
その低い声は、ため息に紛れたけれど、少し震えていたかもしれない。
(この人でも、こんな顔をするんだな…)
意外ではあった。
とはいえ、その苦い思いは理解できるものだったので、アフロディーテは黙って話の続きを待った。
長い黒髪に縁取られたサガの横顔の向こうには幾つもの女神像が、木々の緑に紛れて並んでいる。
暗い教皇宮から眺める外の風景は強すぎる日射しをうけて白く煙るように輝く。ひどく眩しくて、アフロディーテは目を細めた。
女神神殿に奉られた巨大なアテナ・パルテノス神像と違い、聖域のそこかしこに無造作に置かれた数々の女神像は代々の女神を象ったもので、それぞれ纏う衣装も、年齢も雰囲気も違っている。その時代や環境を反映して、特に巨大なものもあれば、掌に収まるほどのレリーフもあった。
サガの視線を追ううちにアフロディーテの目に入ったものが、いつの時代の女神の似姿なのかは判らない。それはほぼ等身大の優雅な青灰色の大理石像で、祈るように空を見つめていた。
―――"あの子"に少し、似ているかもな…
その澄んだまなざしに覚えがある。
サガは再び黙り込んでしまい、アフロディーテには継ぐべき言葉がなかった。
ただ、二人が同じ思いに捕らわれている。
「あの子」のことを考えて、胸が詰まった。
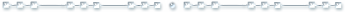
ポプラに囲まれた祠の側に、カミュとアイオリアがぼんやりと坐っていた。
陽光がまたたく木陰に、いつも一緒にいるはずのミロの姿はない。アフロディーテは怪訝そうに、カミュに声をかけた。
「…ミロは?」
「…う、ん…たぶんいつものところじゃないかな…」
少し言いにくそうにカミュが応える。おそらくはアイオリアに気を使ってのことだろう。
「いつものところ」というのは、聖域の最奥にある聖闘士の墓所―――アイオロスの眠る場所である。
「…そう……」
アイオリアは、そのやりとりを聞かないふりをしている。僅かにその眉間に皺が寄るのをアフロディーテは見逃さなかったが、そのことには触れない。もうずっと、触れずにやりすごしてきた。
あの事件から既に五年以上が経ったいまでも、彼らの中でその衝撃は、風化することなく鮮烈なものであり続けた。
そのことに耐えているのはアイオリアひとりではないけれど、彼のその痛々しい沈黙に、身体に纏いつく悲壮に、誰もが言葉を失ってしまう。
アフロディーテは僅かな苛立ちと共に、アイオリアのその頑なな態度を無視し続けてきた。
「……それは困ったな…」
独り言のつもりが聞こえていたらしく、カミュが心配そうにアフロディーテを見上げている。およそミロに係わるあらゆることが彼の心配の種だった。
「あそこに…何か?」
「ああ、いや…こちらの都合だから…」
立ち上がろうとするカミュを止めて、アフロディーテはふわりと笑った。ポプラの葉は、微かな風に鈴のような葉擦れの音を響かせる。
平和な―――平穏な午後の情景は、いつも静かな悲しみに満ちている。
アフロディーテは、祈るような思いで輝く晴天を仰いだ。
あまりにも傷ましい日々に、誰もが少しずつ疲れていた。
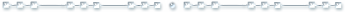
誰もいないと思っていた場所に、それもいて欲しくないと思うほど大切な場所に先客がいることにミロは戸惑った。
アイオロスがいなくなったあの日からずっと、ここで他人に出会うことなど一度もなかった。そもそも、出会うはずが無かった。
叛逆者への墓参など、どんな立場の者にとっても禁忌に決まっている。
―――サガ?
唇だけが、名前の形に動いた。
のどは嗄れ、声は失われて、ミロは動けなくなった。
その後ろ姿が、あまりにもサガに似ていた。
子供の頃、時折見かけた彼の少し寂しそうな後ろ姿―――アイオロスと遠く離れているとき、窓辺でぼんやりとその人のことを考えているときの、見覚えのあるあの背中に似すぎるほど似ているのに、そこにいる人物は黒髪だった。
俯いたまま立ちつくす肩を長い黒髪が縁取って流れている。少し癖のある艶やかな髪は、腕に絡み、抱きかかえたジャスミンの花束にこぼれて―――
不意に振り返った顔は、やはりサガにひどく似ていた―――そう、錯覚した。
「……誰?」
身に纏うものから、聖域に属する高位聖職者であることはすぐに解った。教皇かとも思われたが、アイオロス誅殺を命じた本人が―――まして、この墓所への一切の立入りを禁忌としたその本人がここに存在して良いはずがない。
アイオロスにゆかりの深い、おそらくは神殿の聖職者なのだろう―――禁忌を怖れぬほど彼を愛し、いまなお信じている者に違いない。
「………」
ミロは目の前のその人物が言葉を発するのを待った。
―――このひとは、アイオロスのことをどんな風に知っているのだろう……。
無機質な光沢の仮面の向こう側で、感情が大きくうねるのが解る。動揺だろうか、それとももっと質の深い感情なのだろうか―――その仮面の奥から自分を見据える意志の強さを感じることもできる。ミロは、そっと微笑みかけてみた。
「……ミロ……」
声はどこか懐かしかったが、知っている誰にも似ていない。
自分の名前が知られていたことは意外だったが、黄金聖闘士であればありえないことではない。やはり高位聖職者なのだろう。ミロは返事の代わりにもういちど笑顔をつくった。
「ここには良く来るんですか?……ここにはいつも花が溢れているけど、誰が捧げているんだろうって……ずっと考えてた。」
アイオロスの名を墓石に目で追いながら、ミロは話し始めた。
自分は知らない、アイオロスの知己―――そんな存在を考えたこともなかった。
「もしかしたら…サガじゃないかって…思って………いつも、沢山の花束をここで見つける度、サガが来たのかな……って………そう…思って…いたんだけど……」
そこに立ちつくす人は何も言わない。
一陣の風が通りすぎる。
松葉が揺らぐ音は、海の波に似ていた。
―――あなたは、誰?
それが訊きたかった。
訊いてはいけないことだとは解っていたから、口には出さなかったけれども。
「あの、…サガは…サガのことは知ってますか?……僕たちの大切な人でした…アイオロスがいなくなる前に、行方不明になったきり……それきり…会えないんです……」
やはり、その人は答えなかった。
「……ミロ!」
アフロディーテの声。
その声に、ミロは松林を振り返る。
立ち去るかと思われた黒髪の人物は、傍らに佇んだまま木立に見え隠れしながら近づいてくるアフロディーテを眺めている。やがてアフロディーテは二人の姿に気づき、そして動じた様子もない。
―――……知っている?
「どうしたの?……アフロディーテ?」
「……神殿から呼ばれてるんだ、一緒に行こう」
アフロディーテは二人から少し距離を置いて立ち止まった。第三者を警戒しているせいなのか、何か他に理由があるのか―――
「急ぐの?」
「ああ、すぐにだ」
「……それじゃあ……」
ミロは、傍らのその人に軽く会釈をすると、もう一度だけ問い掛けた。
「また、会えますか?…いろいろ、訊きたいことが……」
その人は、聞き取れないほどの小さな声で、「わからない」と言った。
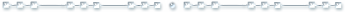
「ねぇ、いまの人、知ってるの?」
「知らないよ」
「アイオロスの知り合いなんだよね?」
「…知らないってば」
神殿に向かう薄暗く長い回廊に、二人の靴音が大きく反響している。足早に歩を進める聖闘士たちを、仮面の巫女達が静かに振り返る。いつもなら気にも留めない光景だったが、ミロはその音もなく行き来する巫女達の姿の中に、あの黒い髪を探していた。
「……ここの人かなぁ?」
「…さあね」
「……怒ってる?アフロディーテ」
「……怒ってなんかいないけど?」
―――嘘だ。
本当は怒っている。
―――サガ、何しに来てたんだ?
問い質すまでもない。ミロに会う為にきたのだ。あの神聖な場所―――アイオロスの墓石がある、あの小さな丘の頂―――ミロにとって、ミロにとってだけ、神聖なあの場所に―――
―――なんのつもりだ……!
あの白い墓標の下に、アイオロスはいない。空の棺が埋まっているだけだ。
それを知っていて、花を捧げていた。サガがどんなつもりでそうしていたのかは理解できなかったししたいとも思わなかったが、無性に腹が立って仕方がなかった。
ミロに会いたいなら、なにもあんな処でなくてもいい。
「神殿内では、お静かに」
巫女に呼びとめられてわれに返った。
「……すみません」
怒りが収まらないまま、挑むような目で巫女を見返すアフロディーテの代わりに、神妙な顔で、ミロが頭を下げた。
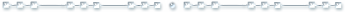
薔薇園には静かに夕暮れが訪れ、遠く、花の垣根の向こうに主のいない風の塔が見える。
(本当はね、少し…疲れたよ……)
この頃は、ひとりきりになるとひどく疲れている自分に気づく。谷間を渡る風に優雅にはなびらを揺らす花の群れも、慰めにならない。
(……どうしたらいいんだろう?)
答えを知っている人はもういない。
その人と植えた薔薇は、こんなにも鮮やかに咲き誇っているのに。
あれは、いつのことだったろうか。
月のない夜、風の塔の観測台から、アイオロスと二人で聖域を見渡したことがある。
霧にかすむ薔薇園の向こうに青白く浮かびあがる神殿群は、蜃気楼のように厭世的でアフロディーテは不安だった。こんな幻のような世界では儚すぎて、自分の存在までが夢や幻になりそうで、悲しくて仕方がなかった。
(ねえ……アイオロス…)
いまはここから見上げる風の塔が幻に見える。主を失って輝きをなくし、やがては荒れ果てるままに崩れてゆくのだろうか―――。
(まるで…悲しみに耐えることが仕事のようだよ……)
失われたそのひとの輝きが強すぎて、いまも落とした影が聖域に焼きついている。
あの日―――あの遠い日々の記憶が、まだ鮮やかな傷口から血を流しつづけている。
―――どうしたらいいんだろう?
そればかり問いつづけている。
to be continued...
ALCYON [ main I contents ]
コハクノバラ 18/Mar/2013 up
続きどうしろと…?!・゚・(ノД`)・゚・と(書いた本人が)泣きたくなる話第2弾ですほんとうにどうしたものか…。「コハクノバラ」は、琥珀の薔薇です。琥珀色をしたバラの花(植物)のことと、琥珀でできたバラの花(宝飾)のことの両方を何か書こうとしていたらしいです(ウロオボエ)。ワタシの脳内妄想聖域には「風の塔」というものが存在しております。妄想の元はアテネのプラカ地区に実在します。そしてこのハナシ、しまい込もうか迷ったのですが、続きに関しては不明でも関連する話はこれからUPしていくと思うので置いておくことにしました。
![]()
![]()
![]()
![]()